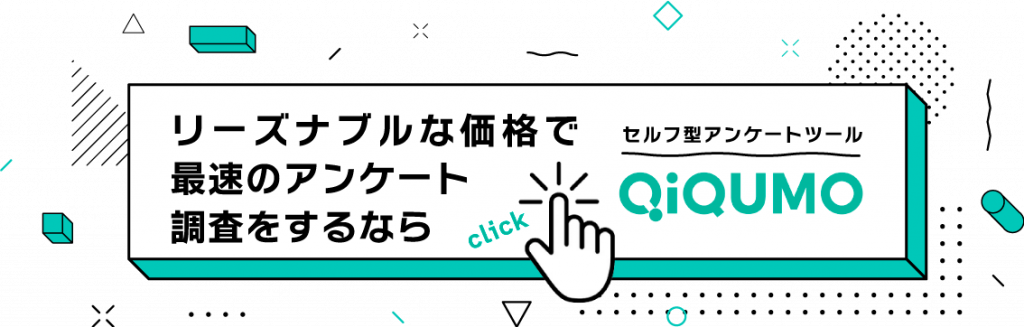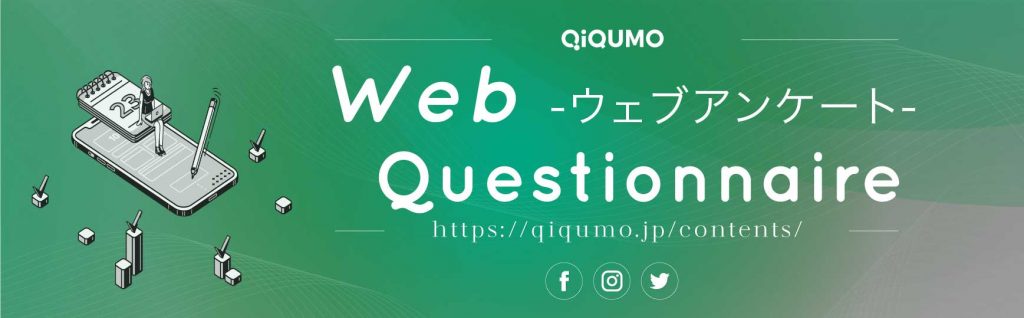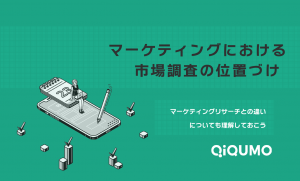マーケティングミックスの視点から調査目的に応じたアンケート調査の種類を紹介

アンケート調査を実施する際には、「何を明らかにするのか」という調査の目的と、マーケティング戦略のなかで調査結果が「どのように活かされるのか」について明確に意識する必要があります。
マーケティングプロセスのなかで実施されるアンケート調査にはさまざまな種類があり、それぞれの段階でのマーケティングの機能との関連を理解することが有益な調査結果を得ることにつながります。
さまざまなアンケート調査の種類について、マーケティングミックスの観点からどんな特徴があるのかについて解説します。
マーケティングとは
モノがあふれている消費社会において、マーケティングは商品やサービスを提供する側にとって欠かすことのできない活動のひとつです。
多様な価値観があるなかで、消費者の心理や行動を理解し、選ばれる商品とその仕組みづくりを行うことがマーケティングの役割といえます。
売るための仕組みを構成する要素は、アメリカマーケティング協会(AMA)のマーケティングの定義(2007年)に示されています。
Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.
マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。(慶應義塾大学 高橋郁夫氏訳)
「顧客、依頼人、パートナー、社会全体」は市場(マーケット)に置き換えられ、市場を相手として「創造」「伝達」「配達」「交換」を行うための活動がマーケティングであると考えることができます。
マーケティングミックス
マーケティングの定義に示される、創造(Creaiting)・伝達(Communicating)・配達(Delivering)・交換(Exchange)は、1960年にE・ジェローム・マッカーシーの著書「ベーシック・マーケティング」で紹介された4P(Product・Promotion・Place・Price)と関連付けることができます。
4Pは企業側の視点からのマーケティングの概念として提唱されたもので、1964年にハーバード・ビジネス・スクールのニールボーデンが「マーケティングミックス」という言葉に置き換えています。
1980年代に入り消費の在り方が高度化すると、マーケティングに買い手側の理解がより一層求められるようになり、4Pのプロダクトアウトの視点から4Cのマーケットインという発想に切り替わりました。
| マーケティングの定義 | 4P企業側(売り手)の視点 | 4C消費者側(買い手)の視点 |
| 創造Creating | 製品Product | 価値Customoer Value |
| 伝達Communicating | プロモーションPromotion | コミュニケーションCommunication |
| 配達Delivering | 流通Place | 利便性Convenience |
| 交換Exchanging | 価格Price | コストCustomer Cost |
4Pと4Cのそれぞれは、コトラーが提唱するマーケティング1.0(製品主義)、マーケティング3.0(価値主導)に対応するものであり、現在はデジタルが前提となるマーケティング5.0にバージョンアップしています。
製品の内容や消費者が重視する価値、プロモーションや企業と顧客のコミュニケーション手段、流通経路と消費者が感じる利便性、商品そのものの価格と消費者が支払う時間や労力を含めたコストのそれぞれは時代とともに中味が変わっていきます。
しかし、4つの要素とそれぞれの関係性には普遍性があり、現在でもマーケティングを理解するうえでの基本と考えることができます。
マーケティングミックスに対応するアンケート調査の種類
4Pと4Cはマーケティングを構成する基本的な要素であり、必要とされる調査の目的に応じたアンケート調査を計画することが必要です。
Creating・価値・製品
製品やサービスが消費者に提供する価値は、直接的な便益のほかに課題解決や自己実現の手段、欲求や願望の実現などさまざまな側面を持っています。
消費者の選択行動を左右する価値の分析として知られているのが、米エモリー大学のJ.N.シェス教授による5つの分類です。
【消費価値の種類】
| 機能的価値 | 機能面、実用面の効用 |
| 感情的価値 | 感情・情緒面に与える効用 |
| 社会的価値 | 対人関係や帰属集団に影響される効用 |
| 認識的価値 | 価値観や好奇心にもとづく効用 |
| 条件的価値 | 季節要因など一時的な条件によって発生する効用 |
これらの価値を持つ製品やサービスを生み出すにはどうすればいいか、現行の製品やサービスがこれらの価値を実現しているかどうかを確かめるためにマーケットリサーチを行います。その方法のひとつであるアンケート調査は以下のような目的で用いられます。
コンセプトテスト
コンセプトテストは、新しい製品の持つ本質的な価値が市場に受け入れられるかどうかを評価するためのマーケットリサーチです。
評価に際して定量的な指標を求める場合にアンケート調査を実施します。
先に上げた消費価値の何を実現するかを決めたものがコンセプトです。コンセプトテストでは以下のような基準を設けて受容性を評価します。
- 理解度
- 新規性
- 信頼度
- 興味・関心・魅力
- 購買意欲
コンセプトで描く消費者にとっての価値が市場に受け入れられるかどうかを評価することが目的であり、定量調査で示された指標をもとに、新規参入や新たな製品の市場投入の可否を判断します。
顧客満足度調査
製品やサービスに対する市場からの反応を把握することが顧客満足度調査の目的です。顧客満足度調査では、以下の指標をもとに顧客満足度を評価します。
- 顧客期待
- 知覚品質
- 知覚価値
- 顧客満足度
- 推奨意向
- ロイヤリティ
(公益財団法人日本生産性本部「JCSI因果モデルの6つの指標)
コンセプトテストと同様に、製品やサービスが実現する消費者にとっての価値が顧客満足度調査の中心的なテーマです。
顧客満足度調査は、既に消費者に提供された製品やサービスに対する直接的な評価であり、商品そのものや販売過程の課題抽出と改善、顧客ニーズや市場動向の把握を目的として行います。
Communicating・プロモーション・コミュニケーション
どんなにすばらしい製品を開発したとしても、それを購入する可能性の高い消費者層に製品の存在を知らしめ、製品の価値を正しく理解してもらうことができなければ販売にはつながりません。
有望なターゲット層への認知を広めて興味関心を引き、購入決断のきっかけを作る一連の活動がマーケティングコミュニケーションです。
マーケティングコミュニケーションの具体的な内容は以下のものです。
- 広告
- 販売促進
- 広報・PR
- ダイレクトマーケティング(DM)
- 人的販売
上記の活動の内容の検討や実施の効果を検証するためにアンケート調査を行います。
クリエイティブテスト
クリエイティブテストは、広告の表現が製品やサービスの価値を伝えるメッセージとして伝わるかどうか、また、どんな広告表現が最も効果的かを検討するために行う受容性調査です。
一般的には数種類のクリエイティブを用意し、それぞれに対する受け止め方を定量的に把握します。
広告効果測定
広告やキャンペーンの成果を定量的に評価するためにアンケート調査を活用します。広告効果測定は期間比較、競合との比較、外部要因の特定などを目的とします。
広告認知、好感度、メッセージに対する評価を主な指標とし、パーチェスファネルの段階や購入意向、NPSなど購入に結びつく度合いと関連付けて評価を行います。
Delivering・流通・利便性
製造業や流通業では販売チャネルもマーケティング の対象領域に含まれます。自社製品を扱う卸売業者や小売業者、また、拠点展開や出店戦略が重要な意味を持つ業種にとって、販売地域を対象とするエリアマーケティングは必要不可欠なマーケティング施策のひとつです。
エリアマーケティングでは地域特性や立地を前提として販売エリア(商圏)や消費特性、競合の動向などを分析します。マーケティングリサーチを行う場合は、商圏に関わる流通事業者と消費者がエリアマーケティングの調査対象です。
ディーラーサーベイ・小売店調査
流通事業者や小売店舗からの情報は営業担当者の日常的な活動のなかで集約されることが一般的ですが、流通事業者を対象とするアンケート調査で自社および競合ブランドとの比較や販売動向などに関する情報収集も行われます。
商圏調査
拠点展開や出店戦略を検討する際に、商圏の設定や地域の販売ポテンシャルを分析するのが商圏調査です。経済センサスや家計調査などの2次データと地域の消費者を対象としたアンケート調査を組み合わせて地域特性を明らかにします。
Exchanging・価格・コスト
価格設定はマーケティング戦略に関わる重要な要素であり、需要と供給によって決まる市場価格に加え、消費価値の対価としての消費者側の感じ方と企業側の製造・流通コストから決定されます。
コストプラスやマークアップといった原価基準や競合他社の価格を基準とする競争価格、スキミングプライスなどの戦略価格が企業側の視点からの価格設定の方法です。
一方、消費者側の価格に抱くイメージからアプローチする心理的価格も価格設定の方法として広く用いられています。
- 名声価格
- 慣習価格
- 段階価格
- 均一価格
- 端数価格
- 抱き合わせ価格
PSM分析
上記の価格設定の方法を踏まえ、消費者側の価格に対する感度を計測することで具体的な金額を設定するのがPSM(Price Sensitivity Measurement)分析です。
PSM分析はアンケート調査の質問項目で「高いと思う価格」「安いと思う価格」「高すぎて買えない価格」「安すぎるから買わない」価格金額を具体的に求めます。
集計結果から「最高価格」「妥協価格」「理想価格」「最低品質保証価格」の4つの価格を算出し、それぞれの位置関係を価格設定の指標とするものです。
アンケート調査はマーケティングリサーチの基本
マーケティングリサーチは定量調査と定性調査に分けられ、アンケート調査は定量調査の手法のひとつでしかありません。しかし、マーケティングリサーチの数多くの調査手法のなかで、消費者の声を確かめるアンケート調査はさまざまなフェイズで活用される重要な調査手法のひとつです。