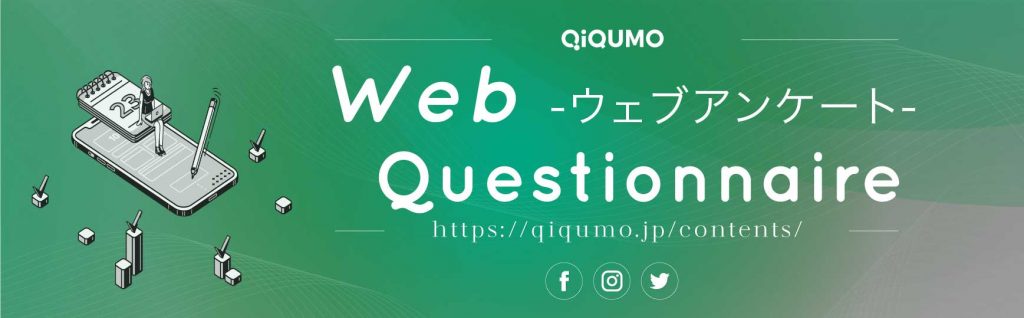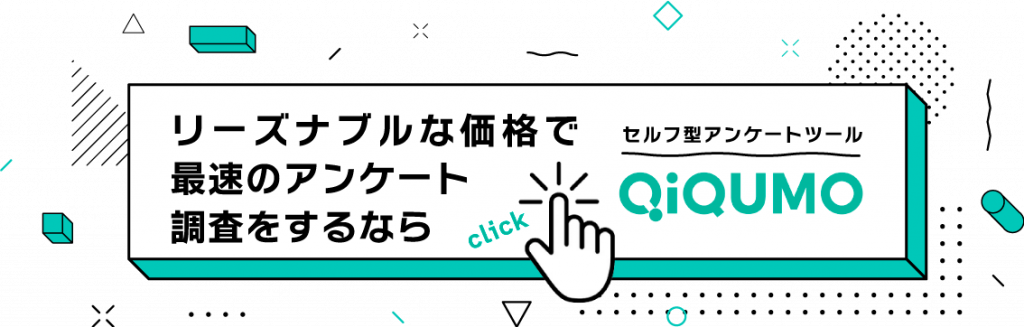お客様アンケートにおけるサービス品質の評価方法

サービスを提供する業態における顧客満足度調査は、モノを提供する業種とは異なった視点からアプローチする必要があります。
サービスとして提供されるものの無形性や生産と消費の同時性、人的要素の重要性など、サービスの質を評価する場合の要素がモノを提供する場合とは大きく異なるからです。
サービスの品質に焦点を当て、顧客満足度調査を行う場合に考えなければならない重要なポイントについて解説します。
サービスの特性
サービスには以下の特性があり、モノ(有形財)とは異なります。
無形性
サービスは受ける行為に基づく経験や体験であり、提供されるコト自体に形はありません。サービスの評価とは見えないものに対する評価であるということになります。
不可分性(生産と消費の同時性)
対人サービスでは、サービスを提供する側(事業者)とされる側(顧客)が同じ場所に同時に存在することでサービスが成立します。
異質性(品質の非均一性)
対人サービスでは、サービスの提供者の人的要素によって提供されるサービスにバラツキが大きく、また、サービスを受ける側の期待水準によってもサービス品質の評価は大きく変動します。
非貯蔵性・消滅性(在庫することができない)
サービスには形がなく、生産と消費が同時に起こることから、商品のように在庫として予め準備しておくことができません。
低い再現性
サービスは工業生産されたモノのように全く同一の品質を受けとることは難しく、対人的要素やサービスを受ける際の状況によってサービスの質は変動します。
認識の困難性
対価の範囲で提供されるサービスはさまざまな要素によって成り立っており、そのなかにはどれだけコストや労力がかかっていても、消費する側に明確に認識されないものも含まれます。また、それはコストに関わらない組織に起因するものである場合など、消費者側が満足の理由に気づけない要素も含まれている場合があります。
サービスの価値
サービスの特性を理解するためにはサービスがもたらす価値の種類についても知っておく必要があります。
機能的価値
サービスが提供する機能とそれがもたらす便益そのものが機能的価値です。後述する共通する事前期待のベースになるサービスの価値の主要な部分です。
関係的価値
生産と消費が同時に行われるサービスでは、提供側と消費者側の関係性がクローズアップされやすくなります。過程品質にかかわる人的対応の望ましさや品質評価項目のひとつである信頼性が関係的価値を形作ります。
経験的価値
消費者にとって受けるサービスが、楽しさや充実感、インスピレーションなど個人として意味のあるものであり、提供されるものに対する納得性が得られることを指します。
心理的・感情的価値
サービスを受ける過程で抱く消費者側の心理的・感情的側面に働く要素として、自分の立場を尊重し自分の立場に即した対応が取られていると受け取られることが価値につながります。
サービスの満足度は事前期待と結果品質の差から生まれる
サービスの特性を踏まえると、サービスを受けることによる便益や満足に対する、消費者側の見積もりや期待は、モノの消費と比べて漠然としたものになりやすいことが挙げられます。
サービスの消費に対する満足度は事前に抱く期待度に大きく左右され、サービスを受けた結果の評価が期待を上回れば満足、下回れば不満足という結果につながります。
サービスの品質評価では消費者側の事前期待がどのように形成され、どのような水準にあるのかを明らかにすることが重要です。
事前期待の対象はサービスの具体的な内容、提供品質、価格です。また、顧客の属性やサービスを消費する時点の状況によっても異なります。
事前期待は以下のタイプに整理できます。
共通する事前期待
宿泊施設であれば、清潔感やきれいさが保たれていること、医療サービスであれば、疾病の回復につながる医療行為を受けられることは誰もが抱く共通認識です。それぞれの業種や業態で一般的とされるサービスを受けられることが共通する事前期待です。
個別的な事前期待
消費者それぞれの個性や事情によりサービス品質に対する要求の異なる部分も事前期待に含まれます。消費者それぞれの違いに対する許容範囲を一定程度設けることもサービス品質を捉える際には重要なポイントです。
状況で変化する事前期待
消費者側の個別の事情に加えて、天候や混雑状況など外部要因が事前期待に影響するケースもあります。生産と消費が同時に行われるサービスではその時に状況に対応する柔軟性が求められます。
潜在的な事前期待
サービスの提供前後のギャップという点では、提供側と消費者側双方が想定していなかった事柄や人的要素がもたらす効果など、定型化されたサービス以外の部分から顧客満足に影響する要素が新たに発見される場合があります。
期待という意味においては満足度に対して大きなインパクトを与える要因にも成りうるため、サービス提供側は日常的なオペレーションのなかでつぶさに把握する取り組みが重要です。
サービス品質の成果指標SURVQUAL
サービス品質を何を持って評価するかを研究した成果をもとに、サービス品質の評価項目として一般化されたのがSURVQUAL(サーブクアル)の品質次元といわれるものです。
以下の5つがサービス品質を評価する際の項目として挙げられています。
| 1.信頼性 | 約束された、または、期待される結果が確実に提供されるか |
| 2.確信性 | 期待する結果が得られるかどうかの予測に対する確信の程度 |
| 3.反応性 | サービス提供の迅速さと意欲 |
| 4.共感性 | 顧客ニーズに対応するためのコミュニケーションのスムーズさと敏感さ |
| 5.有形成 | 施設・設備・人材・ツールなどの適切さ |
また、多摩大学の近藤教授は消費者側の主観的な評価基準として経験品質、過程品質、道具品質を提唱しています。
| 1.結果品質 | 目標達成度メニューと選択可能性カスタマイズの程度プリ / アフターサービスの充実度例外的対応を事後処理の適切さ |
| 2.過程品質 | 知識・技能の水準マンパワーの適切さ礼儀正しさ、プライバシーへの配慮スピード情報提供の充実度と提供方法の適切さ課題への理解力・共感力 |
| 3.道具品質 | 施設設備の充実度施設設備の快適度施設設備の安全性物的要素の美的水準プライバシーへの配慮営業時間・立地条件などの利便性契約内容の明確さ・透明さ苦情等への対応 |
サービス・マーケティング・ミックスの7P
顧客満足度調査はサービス提供者側がマーケティングリサーチの一環として行う調査活動のひとつです。
ここまでサービスの評価要素について見てきましたが、顧客満足度調査をサービス業のマーケティングに活かすためには、企業側の視点と顧客側の視点のすり合わせが必要です。
その前提となるのがサービス業の実行戦略であるマーケティング・ミックスの7Pです。
マーケティング・ミックスについて詳細を知りたい方は「マーケティングミックスの視点から調査目的に応じたアンケート調査の種類を紹介」をご用意していますので、チェックしてみてください。
- 製品(Product)
- 価格(Price)
- 流通(Place)
- プロモーション(Promotion)
- 人材・要員(Perdonnel)
- プロセス(業務・販売プロセス)
- 不安を払拭するための物的要素(Physical Evidence)
上記リストの製品と流通はサービス業に置き換えるとコアサービスとサービスの提供場所が当てはまります。サービスの特性により4Pに加えられるものが、人材・要員、プロセス、物的要素です。
これらに割り当てられる経営リソースが、サービスの品質を確保するうえで十分なものかどうかを検討する必要があります。
サービスの顧客満足度の特性を表す狩野モデル
顧客満足度調査の結果を評価しサービス・マーケティングに活かしていくにあたり、顧客満足度の特性を理解する必要があります。
そのひとつが東京理科大学狩野名誉教授が提唱する「狩野モデル」です。

狩野モデルは製品やサービスの品質要素を分類しモデル化したもので、一般的には以下の5つの品質要素に分解されます。
- 当たり前品質(あって当たり前、ないと不満に感じる要素)
- 一元的品質(あると嬉しいが、ないと不満に感じる要素)
- 魅力的品質(なくても構わないが、あるとより嬉しい要素)
- 無関心品質(顧客満足に影響を与えない要素)
- 逆品質(あると不満につながり、ないほうがよい要素)
これをサービス業に適用した場合、サービスの機能価値を提供するメインのサービスは品質の向上を顧客満足に反映させにくいという特性を持ち、それに対しサービスの副次的な要素ともいえる関係価値や経験価値、心理的価値に着目することが顧客満足度向上につながりやすいという側面があります。
お客さまアンケートの質問項目
顧客満足度調査を目的とするお客さまアンケートを実施する場合、自社が提供するサービスに関連する要素を7Pの視点から切り出し、サービスの価値、事前期待と結果品質、SURVQUALの観点から、顧客満足につながる要素をあぶり出すことが必要です。
webアンケートツールのテンプレートに用意されている、サービスの利用理由や満足度の段階評価とその理由、他人に勧める度合いなどを漠然と質問しても得られるものはありません。
顧客満足度調査でどのポイントを消費者に問うべきかを決める際には、自社のサービスの全体像を明らかにした上で詳細に検討することが重要です。
サービス品質を理解して結果につながる顧客満足度調査を
サービスの品質について解説しましたが、普段、何気なく利用するサービスには、気づかない配慮やきめ細かい工夫が凝らされていることも少なくありません。人的要素の比率が大きいサービスを提供する場合、顧客満足度調査を有効に活用してサービスの改善につなげていくことをおすすめします。